2017年以前、民泊条例といえば通常「特区民泊条例」のことを指していましたが、2018年6月に住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が施行されたことで、各自治体が同法に基づいて定める条例も登場し、これらも「民泊条例」と呼ばれるようになりました。
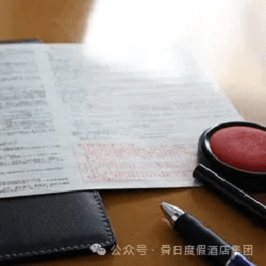
ここでは、各自治体による住宅宿泊事業法に基づいた民泊条例と、「国家戦略特区」による特区民泊条例について詳しく解説します。
民泊条例とは?
民泊条例には以下の2種類があります:
- 住宅宿泊事業法に基づく条例
- 国家戦略特区外国人滞在施設経営事業に関する条例
住宅宿泊事業法に基づく条例
2018年6月に施行された「住宅宿泊事業法」(通称「民泊新法」)では、「住宅」を宿泊施設として提供することが可能になりました。
従来、旅館業法のもとで営業される旅館やホテルは「住居専用地域」などの住宅地域では営業できませんが、住宅宿泊事業法では「住宅」として運営するため、これらの地域でも営業可能です。
しかし、「住居専用地域」は良好な居住環境を保つために設けられている地域であり、観光客が多数訪れることで環境が損なわれる恐れもあるため、自治体ごとに運営可能な期間や地域に制限を設けています。
国家戦略特区外国人滞在施設経営事業に関する条例(特区民泊)
特区民泊は、国家戦略特区の制度に基づき、外国人観光客を対象に住宅を宿泊施設として貸し出す制度です。
もともと旅館業法では条件が厳しく、民泊はグレーゾーンとされてきましたが、特区民泊制度の登場により一定条件下で旅館業法の適用外として運営が可能となりました。
特区民泊の主な条件は以下の通りです:
- 国家戦略特区内にある物件であること
- 貸借契約(定期借家契約)に基づいて貸し出すこと
- 宿泊日数は3泊2日以上であること
- 施設に一定の広さや鍵の設置、清掃義務などの条件を満たすこと
- 外国語による案内の提供が必要
地方自治体ごとの違い
「民泊条例」と言っても、実際の運用内容や規制の厳しさは自治体ごとに異なります。
たとえば、東京都大田区の特区民泊は、建築基準法により旅館やホテルが建てられるエリアに限定されています。その他の自治体でも、住宅地の環境保全を考慮し、学校周辺や住居専用地域での制限など、地域ごとにさまざまなルールが設けられています。
まとめ
旅館業法では対応しきれない新たな宿泊ビジネスに対応するため、特区民泊や住宅宿泊事業法など、さまざまな法制度が整備されています。今後も法改正が予想されるため、定期的に最新の情報を確認することが重要です。